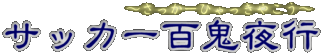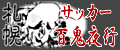2008年Jリーグディビジョン1第13節
コンサドーレ札幌 1-3 名古屋グランパス
得点者:札幌/宮澤
名古屋/マギヌン、玉田、ヨンセン
アウェイで大宮に競り勝ち3勝目を挙げた札幌は、ワールドカップ最終予選によるJ1リーグ中断前の最後の試合となる今節、名古屋グランパスを札幌ドームに迎えました。
名古屋はJリーグ初年度からの参加チーム、いわゆる「オリジナル10」の1つ。前身はトヨタ自動車サッカー部で、プロ化以来使用してきた「名古屋グランパスエイト」の呼称を今季から「名古屋グランパス」に変更しました(運営会社名は株式会社名古屋グランパスエイトのまま)。Jリーグの発足に際し、プロ化を推進していた木之本興三専務理事(当時)が、地域密着を前面に出すためにチーム名に企業名を使用させないと主張したのに対し、賛同していたのは当時まだJSL2部の弱小チームだった住友金属のみで、他のチームの母体企業は「それでは宣伝にならない」と猛反発する中、トヨタの「ヨーロッパのチームはどこも企業名は入っていない。うちはトヨタの"ト"の字も入れない」という一声で流れが大きく変わったことは、NHKの「プロジェクトX」でも扱われたので有名な話ですし、同時に「グランパスエイト」に"ト"入ってますやんというつっこみもまた有名な話で、さらにこの「エイト」も一般に知られている名古屋市の記章"八"から取ったのではなく、実は「トヨタ」の画数8から来ているとのことなのですが、そのエイトがなくなったことでこれで名実共にトヨタの"ト"の字も入らなくなったということになります。
親会社が世界のトヨタという豊富な資金力が背景に、世界的なプレイヤーや監督を招聘しながらもメジャータイトルの獲得は2度の天皇杯(1995年、1999年)のみ。ナビスコカップもベスト4止まりでここ3年は予選敗退、レギュラーシーズンでは1996年の2位が最高で、8位前後の中位程度をうろうろすることが多く、その予算規模や西へも東へも遠征しやすい中部地方の中心都市にホームタウンを構えていることなどを考えれば不思議な成績であることから、サポーターの間では「エイトの呪い」と言われていたのですが、そのエイトを取っ払った今季はかつて名古屋に在籍し、ファンタスティックなプレイで観客を魅了した「ピクシー」ことドラガン・ストイコビッチ氏が監督に就任した今季は、開幕戦こそ京都サンガFCと引き分けたもののその後は6連勝を達成。悲願の優勝に幸先のいいスタートを切ったかに思われましたが、その連勝を東京ヴェルディに止められた第8節を境に、6連勝がウソだったかのように3連敗を喫してしまったことから、「エイトの呪いはまだ生きていた」と嘆いたサポーターも多いとか。あれですかね。捨てたのにいつの間にか部屋に戻ってる呪い人形みたいな。オッドアイの毒舌人形なら良かったんですけど。まきますよ。まきますってば。
まぁWikipediaによれば名古屋は伝統的にゴールデンウィークに弱いらしいのですけど、その後はFC東京に勝利してヴィッセル神戸に引き分けと持ち直し、第12節終了時点で7勝3敗2分と首位の浦和レッズと勝点3差の2位につけています。浦和に離されないためにも下位相手の取りこぼしは避けたいところでしょうが、ところがどっこいなぜか名古屋はこの取りこぼしも伝統的に多いチームで、それが上位争いできなかった所以のひとつなんでしょうが、特に札幌にはあまり分が良くありません。まぁそうは言っても、名古屋はJリーグ初年度以来の16シーズン目、ここまではリーグのタイトルとは今のところ縁がないとはいえ、かといって一度たりともJ2に落ちることなくJリーグ/J1という陽の当たる場所で過ごしてきたのに対し、札幌はクラブ創設してからの13シーズンのうち9シーズンを旧JFLやJ2で過ごしてきたため、そもそも対戦自体がそんなに多くないですし、相性がいいと言ってもここまで3勝2敗1分と特に突出した成績でもないんですが、前回対戦した2002年、そう、出てくる選択肢でことごとくバッドエンド行きの選択肢ばかりを選び続けた札幌が挙げたわずか5勝のうち2勝が名古屋から挙げたものでした。
で、そんな名古屋の力強いアシストがあったにも関わらず異次元の弱さで当時の史上最速記録を更新して降格したコンサドーレ札幌は、それから6年かかってようやく這い出てきました。セミみたいですね。前節3勝目を挙げたとはいえ現状の成績では成虫の寿命が一年というところまで見事なセミっぷりを見せているだけに、いい気分で中断期間を迎えるためにも相性の良さを生かしておきたいところ。その札幌のメンバーは出場停止だった坪内が左サイドバックとしてスタメン復帰を果たした以外は前節勝利した大宮戦と同じ顔ぶれ。
試合は開始から前節と同じように札幌がペースを握る展開となり、クライトンとダヴィを中心に何度かチャンスを作ったあとの前半16分、相手ペナルティエリア付近での混戦からのこぼれ球に左足を振り抜いたFW宮澤のシュートがゴール隅に突き刺さり先制します。ルーキーのプロ初ゴールで意気上がる札幌は守っても日本代表FW玉田との1対1をぎーさんが止め、柴田がノルウェー代表FWヨンセンに臆せずぶつかり、平岡は相変わらず哀しそうな顔をして相手の攻撃を抑え、前がかりになっている名古屋にカウンターを何度かお見舞いするなど理想的な展開で前半をリードしたまま折り返します。
前節も勝ったとはいえ後半は前半のアグレッシブなサッカーが見る影もなく大宮に終始ぺースを握られる展開となり、相手の攻撃に晒され続けていったんは追いつかれてしまいましたが、この試合も後半開始早々にディフェンスラインの乱れからマギヌンにゴールを許して追いつかれてしまいます。その後は再び突き放すチャンスを得ながらも決められず、逆に後半25分にミスを連発して玉田に逆転ゴールを許すとその10分後には吉弘が与えたPKをヨンセンに決められ2点差とされてしまい、結局1-3で破れてしまいました。
この試合の敗因はいくつか挙げられます。ひとつはもちろん名古屋の選手たちとの総合的な技術の差が上げられますが、大宮戦と同じように体力の落ちた後半に相手の攻撃をほとんど止められなくなってしまったこと。集中力の問題と片付けてしまうのは簡単ですが、集中し続けるというのはけっこう大変な作業です。特に守備というのは刻一刻と変化する状況の中、自分のマークしている選手の動き、ボールの動き、味方の動き、スペースなどを見て相手のプレイを予測しながら、チームの戦術上最適なプレイを出来るだけ早く選択して実行する必要があります。イメージとしては車の運転に近いかも知れません。オレはペーパードライバーですけど普段車を運転される方なら、交通量の多い街中を車で運転する時は集中力がいるし、その状態を保ち続けるのはけっこう難しいのがわかるのではないでしょうか。サッカーの守備も同じように、相手の攻撃をクリアしたと思ったらまたすぐ戻ってきて、何とかクリアしたらまたすぐ相手の攻撃がやってくる、というような息の抜けない状況では、車と同じように事故に遭ってしまう確率も上がっちゃいますよね。
ということで後ろを楽にするためにも攻撃の時間を増やしたいところなんですが、そもそも札幌はポゼッションして相手を崩すという攻撃パターンはあまり持ち合わせておらず、というかやりたくても出来ないというのが正直なところなのかも知れませんが、とにかく前線からプレッシャーをかけ相手の選択肢を狭めた上で、ラインを上げてミッドフィールドの密度を上げて出来るだけ高い位置でボールを奪い、一気にゴールまで持っていくというもの。そのためにはチーム全体の連動が必要なわけで、体力が落ちて前からのチェックが効かなくなれば中盤も後手に回り、中盤が後手に回ればラインも怖くて上げられなくなり、ラインが下がればミッドフィールドで間延びしてセカンドボールも拾えなくなり、ボールを奪ってもFWまで遠いのでロングボールを蹴るしかなくなる、でもロングボールを蹴りこんだところで中盤との距離が空いてるのでセカンドボールも拾えず、結果相手ボールになってまた攻められ、集中力が切れてミスが起こり失点、という感じです。ミスが1度くらいならまだカバーできるかも知れませんが、2失点目のようにミスが2回も3回も続くとそりゃ決められますよね。玉田のシュートもうまかったですけど、取るべくして取られた失点だったと思います。
そういう意味では、選手交代もひとつの鍵ではありました。宮澤もゴールはそれはもう美しい弾道のビューテホーなシュートでしたけど、それ以外ではむしろ大宮戦のほうがよかった感じでしたし、前半の最後のほうで既に電池が切れかかってましたから、後半頭から替えるのも手だったとは思うんですが、リードがわずか1点という状況で前節試合中に痛めた平岡の足や週中で風邪をひいた吉弘のコンディションが万全ではないこともあり、監督としてもぎりぎりまで引っ張っておきたかったのかも知れません。ともあれ、前節同様その平岡を交代させた直後に失点してしまったのですから、結果的には失敗ということになるでしょうか。まぁ1点目は平岡が小川をあっさり離してしまったのが原因だったんですけど。
まぁそんなわけで前半の45分で力を使い果たしたという感じの試合だったわけですが、ただ逆に考えれば、前節の大宮といい今節の名古屋といい、少なくとも45分は中上位のチームを相手でも自分たちのやりたいサッカーが通用しているということでもあります。少し前までは相手にすらなっていなかったことを考えると、進歩は進歩だと思います。まぁそんなもんより勝点よこせと言いたい気持ちもないわけではないですが、この45分を少しでも長く続けられるよう、中断期間にトレーニングを行って欲しいと思います。