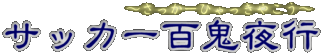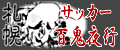2009年Jリーグディビジョン2第14節
徳島ヴォルティス 3-3 コンサドーレ札幌
得点者:札幌/西、紀梨乃x2
徳島/徳重、菅原、登尾
前節栃木SCを決まり手・うっちゃりで下したコンサドーレ札幌は、アウェイで徳島ヴォルティスとの対戦です。Jリーグに参入してから今季で5年目を迎える徳島ヴォルティスは、参入初年度の2005年こそ9位と健闘したものの、その後チームは低迷。2006年からは3年連続最下位。今季最下位ということになれば1999年から2001年までのヴァンフォーレ甲府を超える不名誉な新記録を作ってしまいます。さすがにそれはまずいと思ったか、今季はチームの半分以上の選手が入れ替わる大補強を敢行。そして出来上がったチームに徳重隆明、倉貫一毅、米田兼一郎、六車拓也、登尾顕徳、上野秀章といった元京都の選手がやたらと多いのは、昨季から指揮を執る美濃部直彦監督が長く京都で指導をしていたためでしょうが、それにしても徳重、倉貫、米田に加えて三田光、三木隆司、羽地登志晃といったメンツが名を連ねるスタメンを見ると、なんとなく4~5年前のJ2オールスターという印象を受けますね。しかしさすがに経験豊かな選手が揃っているだけあって開幕から好調を維持、前節終了時点で6勝4敗3分の勝点21で6位につけています。
で、その徳島と同勝点ながら得失点の差で7位につけているコンサドーレ札幌にとっては、この試合で徳島を倒せば順位が入れ替わるだけでなく、前日に5位の水戸ホーリーホックが首位湘南ベルマーレに1-5で大敗しているため、さらに得失点差で水戸を上回り5位にまで順位を上げることができます。前節出場停止だったダニルソンも戻り、久しぶりにベストなメンバーが組める状況になっていただけに、ここで勝っておけばさらに勢いに乗れると思いましたし、前半終了時点ではまったくもって予定通りだったんですけどね。引き分けで終わるなんてつゆほども思いませんでした。
というわけで試合についてですが、開幕以来スタメンを続けてきた主将の上里一将が控えに回り、宮澤とダニルソンのコンビとなった以外は前節と同じメンバー。カズゥはどうやら週中の練習でノブリンを怒らせてしまったようですが、それはさておきノブリンの中ではすっかりFWの2人目と同時にボランチの3人目となった感のある宮澤くん。この状況でも芳賀をボランチで使わないことからも、ノブリンがこのポジションに何を求めているのかは見えますが、視野も広いしボールを持った時の落ち着きもあるので、なんのかの言って宮澤はボランチ向きではあるんでしょうね。その宮澤含めた攻撃陣が機能し、前半はほぼ圧倒的に札幌が試合を支配。相変わらず攻めの中心がクライトンであることは間違いなく、徳島もまずクライトンを止めに入るのですが、マンツーマンでクライトンを抑えきれる選手は少なくともJ2にはいませんし、加えて最近のクライトンは自らが厳しいマークを受けることを承知の上で、2~3人を引き連れて展開するようになり、その結果サイドチェンジなどが有効に作用するようになっています。細かいパス回しがほとんどだったヤンツー時代と、ロングボールでの大きな展開がほとんどだった三浦監督時代を経て、ようやく局面局面において細かいパス回しと大きな展開の使い分けができるようになりましたね。なんというかまぁ、感慨深いですね。創設から13年経ってようやく普通のチームになったとは極力考えない方向で。
いつ点が入ってもおかしくない中、前半18分にコーナーキックから西大伍が何となく池内友彦を彷彿とさせるマークの外し方でヘディングシュートを決め注文通りに先制点をゲットすると、そのわずか1分後にはカウンターから紀梨乃が抜け出して、飛び出してきたGKまで交わして冷静に決めてあっという間に2点のリードをゲット。その後も徳島につけいる隙すら与えず、前半は2-0で終了します。ほんと、この時点では何の問題もない試合内容だったんですけどね。
後半、攻めるしかない徳島は右のサイドバックを寄り攻撃的な麦田和志に代えて打開を図ります。この麦田という選手、「燃えるお兄さん」に出てきてそうな顔をしてなかなかにスピードもある好選手です。いや顔は関係ないですけど、この麦田とマッチアップすることになった大伍が後手に回り、徳島にペースを握られてしまいます。そして後半3分、その大伍が徳島FW佐藤をペナルティエリアの中で後ろから倒してしまいPKを献上。このPKを徳重に決められ1点差に追いつかれてしまいます。PKの判定はちょっと厳しかったとはいえ、先制点のマークの外し方が池内っぽかった大伍ですが、得点は取るけど失点の原因にもなるあたりも池内が乗り移ったかのようです。
2-0から2-1になって俄然勢いづく徳島ですが、札幌もがっくり来るかと思いきや、同点にされてからわずか5分後の後半9分、ここ最近はポストプレイもうまくなってきた紀梨乃が、センターサークルの中で落としたボールを宮澤がダイレクトでクライトンにパス、このボールをクライトンがダイレクトで送ったボールに、走り出していた紀梨乃が自慢のスピードで相手を振り切り、そのまま右足で決め3点目をゲットし、再び2点差に突き放しました。
1点差に詰め寄りさあ俺たちの戦いはこれからだ、というタイミングで再び2点差にされれば、たいていのチームはがっくり来るものです。しかしさすがに上位にいるだけあって徳島も下を向いたりはしませんでした。さらに追加点を取ったとはいえ、やはり連戦と移動の疲れはあったのか、後半からわずかに出足が遅くなってきており、明らかに札幌のプレスが効かなくなってきています。プレスをかけて囲い込んでボールを奪うのが基本線のやり方だと、そのプレスがかかりにくくなると、ボールを奪うためには余計に走らないといけなくなります。余計に走ればそのぶん疲労が増し、疲労が増せば運動量も落ち、運動量が落ちればプレスもかかりにくくなり、プレスがかからなければさらにボールを追っかける時間が長くなるという悪循環を引き起こします。再び2点のリードを得たものの、前半のサッカーは見る影もなくペースとしては相変わらず徳島。さらに前半で足を痛めていたダニルソンを引っ込めざるを得なくなったことも災いし、攻撃的な選手を次々と投入する徳島に押される一方となってきます。やばいな、という空気が立ちこめてしばらく経った後半29分、芳賀を入れて強化したはずの右サイドを破られ、どフリーの菅原(室蘭大谷高校出身)に頭で決められると、もう徳島の勢いを食い止めることができず、そのわずか3分後にはコーナーキックから登尾に頭で決められてついに同点とされてしまいます。ここしばらくは割と安定していた荒谷僧正が、まるで優也が乗り移ったかのような軽快な飛び出し失敗を見せたわけですが、登尾には一応DFが身体を寄せていましたから、あそこは別段無理してはじきに行く必要はなかったと思うんですが、ああいうプレイが出てしまうのもチーム的に追い詰められていたということなんでしょうね。
その後札幌もなんとかサイドの突き放しにかかろうとはするものの、選手たちは足かせでもはめられたかのように動きが重く、逆にノブリンが「3-4にされてもおかしくはなかった」というように、セカンドボールもほとんど相手に抑えられる有様で、大西主審が試合終了のホイッスルを鳴らした瞬間、引き分けて悔しいよりもホッとしたというのが正直なところ。
さてどうでもいい話をすると、実はここポカリスエットスタジアムでの札幌は、鳴門海峡の渦潮が幻夢界を発生させているためなのか、ここでの徳島対札幌戦は必ずドローになるようです。2005年の初対戦で試合終了間際に追いつかれドローとなった試合を皮切りに、その年の2回目のアウェイ戦でも1-1のドロー。翌2006年も2試合とも0-0でした。2007年は1戦目に3-0で勝ってようやく解呪に成功したと思ったら、次のアウェイ戦ではきっちり0-3で負けたという事実もあります。つじつま合わせにもほどがあるってもんです。そう考えればこの結果も幻夢界のせいなのかも知れませんよ。大谷地神社でお祓いしたほうがいいかもしれませんね。
まぁそんなオカルトチックなことを本気で信じているわけではないのですが、2点のリードを追いつかれたことも今のチームの実力なんでしょう。ただしそれと同時に、ここ6試合は10人となった横浜FC戦とアビスパ福岡戦の2試合以外は全ての試合で3点以上取っていること、その横浜FC戦と福岡戦は無失点に抑えていることもまた実力と言えると思います。まぁ実力あるなら退場せんでも0点に抑えてくれという気もしますが、今はまだそういった「強さと脆さ」が同居しているのがコンサドーレ札幌というチームなのだと思います。そうですね。飛行機に例えるなら、零式艦上戦闘機です。あ、そう考えるとちょっとかっこいい。